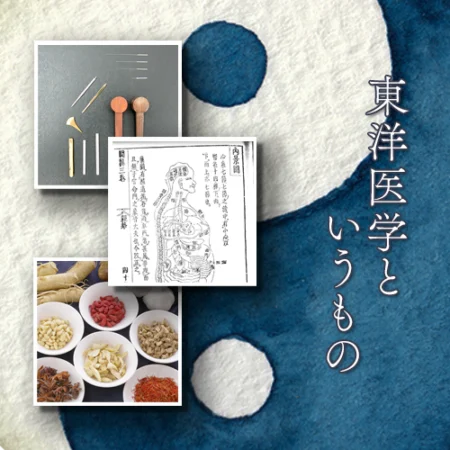病は気から①

「病は気から」という言葉は、耳にすることがよくあります。
【病気は気の持ちようによって、良くも悪くもなる】という意味が辞書に載っていますが、同義語に「百病は気から生ず」と記載があります。
実は前者と後者ではやや意味合いが異なります。
先に後者の話から行くと、東洋医学の書籍には、【百病は気から生ず】というのに二つのパターンが出てきます。
まず一つ目は、外感病と呼ばれるもの。
自然には、風気、寒気、暑気、湿気、燥気、火気といった種類の気があります。
これらの気は季節や天候の変化に従いコロコロと変わっていきます。
これらの気によって体内環境が乱されることから始まる病気のことを言います。
つまり、人体の外の気に感じて起こる病なので外感病と言うのです。
先ほど紹介したように風の気などによって生じる病ですので、「病は気から」の一つのパターンと言えます。
そしてもう一つは、内傷病と呼ばれるものです。
人間には感情があります。
東洋医学ではそれを七情といい、【怒、喜、思、憂、悲、恐、驚】に分けられます。
例えば、怒ると気が上に昇ります。思う(思考)と気が結ばれます。
このような気の変化が体内環境を乱すことから始まる病気のことを言います。
つまり、これらの感情は体の内側から生じてくるので、内傷病というわけです。
どちらかというとこちらの方が「病は気から」のイメージに近いですね。
ここまでの話は「百病は内外の気の乱れから始まる」という意味での「病は気から」の話でした。
次に「病気は気の持ちようで良くも悪くもなる」という意味における話ですが、長くなったので次回に。