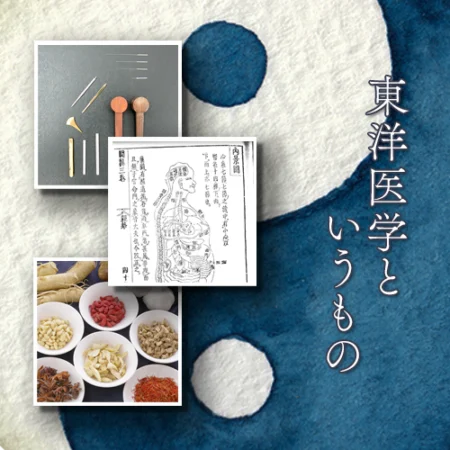ウィルスと東洋医学。

「東洋医学では、ウイルスによる病気をどのように考えるのか?」
以前より患者さんから出ていた質問なのですが、こんなタイミングなので今日はこの話題を取り上げたいと思います。
まず、東洋医学において過去の時代にウイルスを認識していたかというと、そういう記載はありません。
しかし、インフルエンザウイルスによる発熱性の疾患の記載はありますし、今回のコロナウイルスによって生じる咳や発熱の症状が人々の間で流行るというようなことも書かれています。
昔からウィルスによる疾患は存在し、それが流行したりするという現象も普通に存在していたようです。
東洋医学においては、目に見えないウイルスが起こす疾患を「外邪」として考えます。
外邪とは大気の動きである風気、大気の温度状況の寒気と熱気、そして湿度の状況による燥気と湿気が、人間の恒常性を乱した時に呼びます。
それらの強さや性質により、様々な症状が現れるという考えです。
例えば、インフルエンザウイルスによる高熱は、強い寒気により体表が閉ざされたことにより、その寒気を取り除こうと身体が思いっきり熱産生をすることで起こります。
そのように今回のコロナウイルスを分析すると①咳などの呼吸器症状②身体のだるさ③発熱があるようですが、高熱は主ではないようですので、おそらく寒気ではなく熱気が絡んでいるのと、乾燥しやすい状況は肺に影響がでやすくなるので燥気もキーポイントと推測します。
そこで【Weather Spark(https://ja.weatherspark.com/)】というサイトを参考に2019年11月と12月の武漢の気候を調べてみると、例年乾燥する時期のようですし、2019年は平均気温より高い日が多くありました。
日本でも暖冬で変に暖かい日が多かったので、季節外れの暖かさが人間にとっての熱邪になったのかと思われます。※あくまで私見です。
このように普段の気候と違った気象状況になった時、ウイルスの感染力が強くなるのか、もしくは人間の免疫力が落ちるのかはわかりませんが、流行が起きやすくなります。
東洋医学の古書にも、天の気の循環が普段と違う状況において、人々の病気が起きやすくなるとの記載があります。
このような時における東洋医学の対処法はあくまで人間側にあります。
つまり、人間が外邪にやられなければ発病することはないということです。
自身の体調をしっかりと調えること、そして邪気を払う=身を清めることが対処法となります。
今回は多くの方の健康が乱されているのと、さらには社会の動きまで乱されているとのことで、早く終息することを祈るばかりです。